 |
 |
 |
波太神社のお祭り
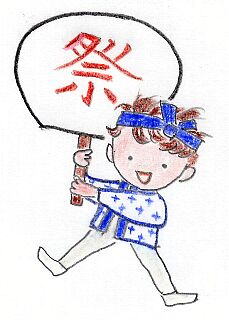
祭りと言えば波太神社の祭りがあり、神社の歴史を見ると古代から由緒ある神社であることが窺(うか)がえる。
往古の祭礼は2月と6月の初丑(うし)の日に行われており、丑祭りとも言われていた。
6月の祭りは暑い時期と農繁期のため、明治以降、10月に行われるようになった。
戦前は府社として祭祀(さいし)されていて、春の大祭には大阪府から神職の服装をした係の役人2・3人が参列し、神主さんを先頭に「コボコボ」と鳴る木靴を参道の石畳に鳴らしながら拝殿に進んで行ったものである。
当日は大変寒い日が多く小学生であった私達は拝殿の下に整列し神主さんのお祓いを受けた。
半ズボン姿の私達は式の始まる一時間も前から整列して震え上ったもので、それが嫌で当日はズル休みをした生徒もいた。
現在では氏子総代や、お宮の役員方がお参りされている。
秋祭りは10月10日と11日であったが、最近では10月の第2日曜日が宵宮で、翌日の祝日が本宮となった。
残されていた資料では「やぐら」は往古には4・50台あったが、大正期には20台余りとなり、更に戦後には18台に減少した。
最近になりお祭りへの市民意識の高まりから各地区の「やぐら」が大修復・新調され、今は20台となっている。
宵宮には「やぐら」の宮入りがあり、3台から5台を一組にし、鳥居手前の踊り場で時間を区切り曳行し、最後に鳥居をくぐり参道を一気に走り抜け石の階段を駆け上る。
この勇壮な場面は有名で、一見の価値があるので皆様にもお薦めする。翌日の本宮には神社から尾崎のエビノ浜まで神輿渡御の行事がある。
これも戦前には神主さんが白馬に乗り先頭を行き、続いて神具箱、槍や鉾を担いだ人達が行列をつくり、その後を赤い鬼の面をかぶった行司に先導された重量約1トンの神輿を3・4十人が担いで練り歩きながらお渡りしたものである。
お神輿は市内の氏子を8組に分け年番で担当することになっており、年番に当たった組は8年に1度のことで、大変な張り切りようでお渡りをするのである。
当クラブ顧問の辻先生在住の新町地区が伝統的に氏子内でも神輿の練り歩きが一番上手であり、この組が年番の時は見物人を魅了させるのが有名である。
前号の「虫送り」の行事は単に害虫退治だけではなく、豊年祈願のお祭り行事であった。お詫びし訂正する。